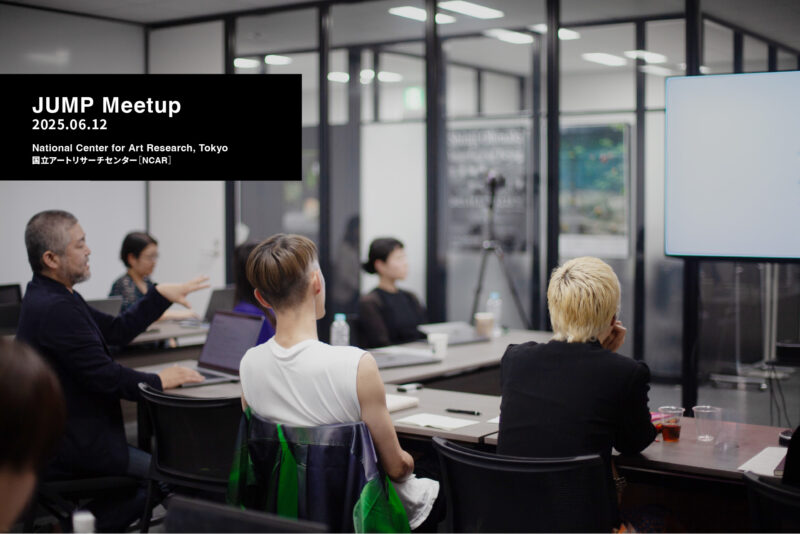※1:塚本麻莉さんが選ぶ極私的「20年間のベスト展覧会」。2004〜24年のなかで記憶に残る展覧会は?
【Tokyo Art Beat 20周年特集】(Tokyo Art Beat、2024年7月19日公開)
コラボレーションの体験談
ひとくちに「現代アート」といっても、そこに携わる人々の職能はさまざま。アーティストやキュレーターといった表舞台に名前が出る仕事だけでなく、展覧会の設営、作品の運搬など、多くの人々の働きによってその世界は支えられています。
高知県立美術館・主任学芸員の塚本麻莉さんは、高校時代、図書室で手にした本をきっかけに絵画の修復に憧れて美術大学に進学しました。その後時は経ち、現代アートのキュレーターになったいま、JUMPのプロジェクトとして、新井健と谷川果菜絵によるアーティストデュオ・MESとともにロサンゼルス現代美術館での展示を計画しています。いったい、そこにはどんな変遷があったのでしょうか? そのキャリアを紐解いていくと、作品を「残す」ことにこだわったキュレーターとしての特別な想いが見えてきました。
聞き手・構成:萩原 雄太 撮影:仲田 絵美 編集:川村 庸子
保存修復に打ち込んだ学生時代
塚本さんは、キュレーターとして働く前は保存修復家を目指していたそうですが、いったい、なぜ美術の修復に興味を持ったのでしょうか?
塚本:もともと絵を描くことがとても好きだったんですが、高校生くらいになると、ずっと絵を描いていられるほどではないな……と、自分の限界も感じていたんです。また、学生時代には美術に限らず歴史を学ぶことも好きでした。そこで、美術と歴史という両方の好きなことをいかせる仕事はないかなと考えていたとき、たまたま高校の図書室でシスティーナ礼拝堂の修復についての本に出合ったんです。そこから修復家という仕事に興味を抱き、愛知県立芸術大学に進学しました。
学部時代には、レンブラント・ファン・レイン(17世紀に活躍したオランダの画家)の絵画技法について研究していました。そして、東京藝術大学大学院の文化財保存学専攻に進学し、2年間、ひたすら油彩画の修復作業に時間を費やしました。東京藝術大学大学美術館に収蔵されている卒業生の自画像や、全国の美術館から寄せられる絵画など、修復を待っている作品は数え切れないほどあったので、それを教授の指導のもと修復する日々。絵画の修復は、とにかく手を動かしながら基礎を学ばなければなりません。当時は、美術館に行く時間も惜しんで作業に明け暮れていました。
美術品は、それを制作したアーティストだけでなく、それを後世に残すためにも数多くの人々が努力を積み重ねています。自分もそんなひとりであることを実感できるのが、修復の喜びでしたね。
ところで、修復に打ち込んでいた当時、現代アートの世界は塚本さんの目にどのように映っていたのでしょうか?
塚本:周りにはアーティスト志望の友達もいたし、ある程度の興味はありました。ただ、みんなとても博識だし、アーティストの話を聞いても何を言ってるのかよくわからない……。作品をどう受け止めたらいいかも、どういうふうに見たらいいのかも理解できなかったんです。関心はあったものの、自分からは遠い存在という印象でしたね。卒業後、まさか自分が現代アートを扱うとは考えていませんでした。
がむしゃらに経験を積み重ねる
いったい、どのような経緯で現代アートを仕事にすることになったのでしょうか?
塚本:成り行きとしか言いようがないんですが……(苦笑)。大学院卒業後、保存修復家としての仕事に就きたかったものの、現実的には難しかった。そこで、2年間東京の美術品オークション会社に就職しました。油彩画に限らず日本画や陶磁などさまざまなジャンルの作品を見られる環境や、作品解説を書く仕事などは楽しかったのですが、一方でコマーシャルの世界に自分が向いていないことを自覚するようになります。そんなとき、たまたま見つけた高知県立美術館の学芸員募集に応募したら合格することができたんです。
高知県立美術館で仕事をはじめてから、現代アートを扱うようになったんですね。
塚本:はい。ものすごく強い思いがあってキュレーターになったのではなく、流されるままに進んでいったら行き着いたようなところがあります。だから、美術館にひたすら足を運んで展覧会を観て、現場でがむしゃらに経験を積み重ねて、なんとか学芸員、キュレーターとしての仕事を覚えていきました。
最初に学芸員としてかかわった展覧会が「高橋コレクションマインドフルネス!2016」でした。これは、精神科医で日本屈指の現代アートコレクターである高橋龍太郎さんが持つコレクションの展覧会。メインの学芸員をサポートするサブ担当として、どのように展覧会をつくっていくのかを学びました。
特に印象深かったのが、作品のインストール作業です。作品を会場に並べるとき、繊細なテクスチャーの作品をインパクトの強い作品の横に置くと埋もれてしまいますし、置き方ひとつで作品の印象は変わる。作品の特性に合わせて配置することによって「場が締まる」とでもいうような感覚を学んでいきました。当時は必死でしたが、いま考えると、それがキュレーションを学んだ第一歩のような気がしますね。
では、キュレーターとして「自立した」と感じた瞬間はありますか?
塚本:初めて「キュレーター」という肩書を名乗ったときでしょうか。高知県須崎市には、「現代地方譚」というアーティスト・イン・レジデンス事業があります。昨年亡くなられた竹﨑和征さんという高知県須崎市出身の画家がこの事業の立ち上げメンバーのひとりなのですが、現代地方譚の5回目(2018年)で、レジデンス作家の展覧会とは別に、地元アーティストのグループ展の企画をわたしに任せてくれました。このとき初めて学芸員ではなく「キュレーター」と名乗って作品が生まれる過程に並走し、アーティストとやり取りして解説文などを執筆しました。こうやって展示をつくればいいんだ! という感覚を体得していきましたね。
塚本さんのプロフィールには「作家の実践を土地の文脈に接続しながら世に問う」とありますが、具体的にはどのような実践を行ってきたのでしょうか?
塚本:2020年に高知県立美術館で開催した「ARTIST FOCUS #01 竹﨑和征 雨が降って晴れた日」が、このプロフィールを象徴しているかもしれません。この展覧会は、わたしが高知県立美術館で自主企画した初めての現代アート展であり、高知ゆかりのアーティストを紹介するシリーズとして現在も続いているもの。その第1回目が、先ほどもお名前を上げた竹﨑さんの個展だったのですが、作家の実践と展示空間とが噛み合って、まさに、「いま・ここ」でしかできない展覧会になりました。とても深い達成感がありましたね。
この展覧会について、以前、塚本さんは「作家の作風が深化する過程を間近で見た経験は忘れがたく、学芸員として大きな喜びだった」※1と書いています。これは、修復の仕事では味わえない喜びですよね。
塚本:そうですね。展覧会の準備期間を通じて竹﨑さんの作風が変化し、結果的に、アーティストとしてのさらなる飛躍につながったように感じます。そうやって、アーティストが変化する瞬間に立ち会えたのはとてもうれしかったし、誇らしくも感じました。


「ARTIST FOCUS #01 竹﨑和征 雨が降って晴れた日」高知県立美術館(2020年)
撮影:田中 和人
近年は、山口県周防大島町にある日本ハワイ移民資料館で行われた「原田裕規 個展 やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」(2023年)をはじめ、高知以外での活動も目立っていますね。
塚本:アーティストとタイミングが合えば、高知県立美術館の仕事としてではなく、自主的に展覧会を企画することがあります。原田さんの展覧会も、彼との自主企画ですね。ハワイ移民を多く出した山口県の周防大島にある資料館で、ハワイ移民をテーマに制作された原田さんの「シャドーイング」シリーズを発表できた稀有な展覧会でした。同作は展覧会の終了後、同館に収蔵、常設展示されることになりました。展覧会ごとにその目的は異なるのですが、わたしがやりたいのは、アーティストの仕事を世のなかに出し、それを残していくこと。アーティストと一緒に展覧会をつくる過程を経験し、その過程を含めて、後世に残していきたいと考えています。
「残す」というのは、修復に打ち込み、美術を次の世代に手渡すことの価値を知っている塚本さんだからこその感覚かもしれませんね。
塚本:そうですね。もちろん残すことだけではなく、作品を広めたり、鑑賞者に楽しんでもらったりすることも目的のひとつ。ただ、広めることだけに満足するのではなく、積み重ねた思考を文章や図録にしながらアーティストの活動とともに残していきたいです。

「原田裕規 個展 やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」日本ハワイ移民資料館(2023年)
撮影:松見 拓也
パフォーマンス・アートという挑戦
今回、JUMPではMESとともにロサンゼルス現代美術館での展示が予定されています。今回、なぜかれらとのコラボレーションを選択されたのでしょうか?
塚本:まず、今回展示を行うのは、ロサンゼルス現代美術館のなかでも分館である「ゲフィン・コンテンポラリー」(以下、ゲフィン)という建物です。本館のほうはいわゆる美術館らしいホワイトキューブなのですが、ゲフィンは、警察車両の倉庫をリノベーションした建物。一般的な日本のミュージアムより、奥行きも天井高もかなりあります。
そこで、向こうのキュレーターから、ゲフィンを使うなら絵画やインスタレーションではなくパフォーマンスのほうがいい、という提案がありました。けれども、わたしはどちらかというと絵画や立体などの「モノ」作品に強く、パフォーマンスの企画を手掛けたことはほとんどありません。アーティストを選択する際にも一筋縄ではいかなかったので、調整するのに時間がかかりましたね。
確かに、作品を展示する場合と、パフォーマンスを上演する場合には、必要とされる文法も大きく異なりますね。
塚本:MESに声をかけたのは、《WAX P-L/R-A/E-Y》という作品の映像を見たことがきっかけです。指先につけたロウソクに火を灯し、手に蝋が伝い落ちていくというパフォーマンス映像は、見ているこちらの身体までヒリヒリとした痛みを感じさせるものです。戦争が絵空事ではなくなった現代に対する、鮮烈な批判精神をもったものだとも思いました。
それに、MESはパフォーマンスのみならず、インスタレーションとして展開できる空間的な広がりをもった作品の制作も期待できます。かれらがつくるパフォーマンスやインスタレーションであれば、ロサンゼルスの観客にも受け入れられるのではないかと考えました。
MESの作品にはクラブカルチャー、ファッション、アクティビズムなどの別ジャンルとの親和性もあり、現代アート以外の観客にリーチすることも期待できますね。では、現在のところ、MESとどのような作品をつくろうと考えているのでしょうか?
塚本:今回、MESが着目したのが、高知県出身の無政府主義者であり、思想家の幸徳秋水です。大逆事件※2で死刑となった彼のことは、高知在住のわたしでもなかなか触れる機会がありませんでした。とてもおもしろい人物に注目したな、と驚きました。
また、もう一つ、作品に影響する可能性があるのが、アメリカ合衆国における現在の状況です。第2次トランプ政権以降、移民に対する強硬な政策をはじめ、社会全体が激しく揺れ動いています。MESのふたりであれば、そのような政治的な動きを身体的にキャッチして、作品としてアウトプットしてくれるのではないかと期待していますね。
※2:1910年、明治天皇暗殺を企てたとして、数百人の社会主義者・無政府主義者が逮捕・検挙された事件。秋水ら12名が処刑されたものの、政府により大部分が捏造された冤罪事件であると言われている。
ロサンゼルスと高知を接続する回路
作品を創作するにあたって、どのようなリサーチが進んでいるのでしょうか?
塚本:2025年5月にMESのふたりが高知に訪れ、高知県立美術館を視察し、所蔵している幸徳秋水の甥、幸徳幸衛の作品を閲覧しました。さらに高知市立自由民権記念館や秋水のふるさとである四万十市にある彼の墓を訪れ、手を合わせています。MESが訪れた高知市のバーでは、オーナーが秋水の遠い親戚であることが偶然判明し、家系図を見せてもらうといったサプライズもあったようです。
また、6月には10日間のロサンゼルスでのリサーチを実施しています。まず訪れたのは会場となるゲフィン・コンテンポラリー。実際に訪ねると壁もなくだだっ広いスペースで、現地のキュレーターが「普通の展示には向いていない」と話していたことが腑に落ちました。一方で、照明などの配置はフレキシブルにできるので、パフォーマンスには最適ですね。
このほかにも、第二次世界大戦中の日系アメリカ人収容所のひとつ、マンザナー強制収容所にも足を運びました。この視察が、個人的には、今回最も強烈な体験でしたね。ロサンゼルスから車で何時間もかかる砂漠の真んなかに、かつて1万人以上の日系人を連行した強制収容所が建てられた。強制収容所といっても、実態はほとんど町に近いスケールであることが、実際に訪れたことで体感できました。当時の人種差別的な政策は、いまのアメリカの移民に対する政策とも重なります。もしかしたら今後、ロサンゼルスと高知を接続する回路として、そういった視点も展示のなかに織り込まれていくかもしれません。

四万十市立図書館幸徳秋水文庫
撮影:塚本 麻莉

ゲフィン・コンテンポラリーでの打ち合わせ風景
撮影:半田 樹里(国立アートリサーチセンター)
ロサンゼルスでは、どのような鑑賞者に足を運んでもらいたいと考えていますか?
塚本:ロサンゼルスには日系のコミュニティがいくつも存在しています。会場となるゲフィンはリトルトーキョーのすぐ近くに位置しているので、日系人や現地で暮らす日本人の方々にも、展覧会を見て何かを感じてほしいなと思いますね。
日系人のほかにも、ロサンゼルスには、海を渡って土地に根づいた方々がたくさん暮らしており、人々の背景は日本よりもずっと多様です。そんな場所で、どのように作品を現地の人々へと響かせられるのかについては、今後考えなければいけない課題だと思います。
ただ、誰もが持つ「身体」というメディアを使うパフォーマンス・アートだからこそ、多様な背景の人々が楽しめる展覧会になるかもしれませんね。ところで、ロサンゼルスの展示に向けて、JUMPのメンター陣からはどんなアドバイスがありましたか?
塚本:高知県立美術館の安田篤生館長からは、アーティスト選考で現地との調整を行っているときに「逃げちゃいけないよ」とアドバイスをもらいました。言語の壁がありますし、相手に強く主張されると、そのまま向こうの意見を飲み込んでしまいそうになるシーンがありました。けれども、ただ引き下がるのではなく、ちゃんとこちらの要望を主張しながら対等な立場で展覧会をつくっていかなければならない。そんなマインドを持つ上で、とても大切なアドバイスでした。
また、国立アートリサーチセンター長の片岡真実さんからも、いくつものアドバイスをいただいています。片岡さんは、自分の体験を踏まえて「その選択肢を取った場合は、長期的にはこういうリスクがあるかもしれませんね」と、具体的な意見をくれるので、判断に迷ったときは頼りにしていますね。
では、今後、JUMPを通じてどのような経験を培っていきたいと考えていますか?
塚本:まず、パフォーマンス・アーティストと協働するのは、わたし自身にとって初めての挑戦。ここから何を得られるのか、いまからわくわくしています。また、パフォーマンス・アートは、瞬間的な力を発揮するものであり、「残す」という概念とは対極にあるもの。これを、どのように残していけるのかを考えていきたいですね。
今回、国際的な舞台で展示を行うことで、日本で行う展示とどのような差が生まれるのかも気になっているポイントです。ロサンゼルスでの展示が終了したあとは、高知県立美術館でも開催を予定しています。きっと、ロサンゼルスと高知とでは観客のリアクションもまったく異なるでしょう。いったい、どのような反応の差が生まれ、それをどのように解釈できるのか、いまからとても楽しみにしています。
2025年8月22日
塚本 麻莉
高知県立美術館 主任学芸員1989年大阪府生まれ。高知県拠点。
2014年東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻修了。2016年より現職。
保存修復の知識を背景に、「残すべきものは何か」を問いつつ、会場ごとの地域性や特性をいかしたキュレーションを行う。開催地の歴史や文化を踏まえた「この場所でしかできない表現」を重視し、作家の実践を土地の文脈に接続しながら世に問う活動を続けている。