阿部 航太(アートディレクター)/椙尾 信也(ウェブデザイナー)/川村 庸子(編集)/萩原 雄太(ライター)
メンバー & 美術館
コラボレーター
リスボン – 山口
ベンジャミン・ウェイル
CAM グルベンキアン・モダンアートセンター ディレクターフランス・パリ生まれ。 イギリス、アメリカ合衆国、そしてイベリア半島の現代アートに関連する機関で多くの要職を歴任し、2021年より現職。
キャリアの大部分を通じ、メディアアートとニューメディアアートの分野において、新進気鋭のアーティストから実績のあるアーティストまで幅広い委嘱作品の制作に注力してきた。1995年には、オンライン作品の制作に特化した初のデジタルスタジオ「adaweb」を共同設立。ジェニー・ホルツァー、ジュリア・シェア、ダグ・エイトケン、ローレンス・ワイナーらと協働した。 その後、インスティテュート・オブ・コンテンポラリーアート(イギリス・ロンドン)ニューメディア部門のディレクター、サンフランシスコ近代美術館のメディアアートキュレーター、テクノロジーを用いた新たな芸術表現の創作と発表を目的としたラボラル:アート&インダストリアル・クリエイション・センター(スペイン・ヒホン)の芸術監督を経て 2014年に、セントロ・ボッティン・アートセンター(スペイン・サンタンデール)の芸術監督に就任。多くの展覧会を企画した。 そのほか、現代アートに関する講演や、プリンセス・オブ・アストゥリアス賞、ループ・アートフェアなどの審査員も務めた。

ロサンゼルス – 高知
アレックス・スローン
ロサンゼルス現代美術館 アソシエイト・キュレーターイギリス生まれ。MoMA PS1(アメリカ合衆国・ニューヨーク)のアシスタント・キュレーターを務めたのち、2021年より現職。
近年企画した展覧会には、ワエル・シャウキーの映像インスタレーション作品《Drama1882》をアメリカ合衆国で初公開した「Wael Shawky: Drama 1882」(2025年)、2023年のヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞(ダンス部門)を受賞したシモーヌ・フォルティの巡回展「Simone Forti」(2023年)、カール・クレイグの《Party/After-Party》やオペラ・パフォーマンス《Sun & Sea》(2021年)などがある。また、ロサンゼルス現代美術館(MOCA)の代表的なライブアートシリーズ「Wonmi’s WAREHOUSE Programs」を企画しており、最近ではナジェージダ・トロコンニコワ(プッシー・ライオット)、ダイナスティ・ハンドバッグ、モライア・エヴァンス、リギア・ルイスらの委嘱作品や初演パフォーマンスを手がけた。

撮影:Carlos Vela Prado
シドニー – 滋賀
メラニー・イーストバーン
ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館 シニア・キュレーターオーストラリア・ダッボー生まれ。オーストラリア国立大学にて美術史およびキュレーター学を学び、パワーハウス・ミュージアム(オーストラリア・シドニー)、カンボジア国立博物館、オーストラリア国立美術館のアジア美術キュレーターを経て、2016年より現職。
企画した展覧会には、李禹煥による「Lee Ufan: Quiet Resonance」(2024年)、江戸時代から現代までの日本の妖怪・幽霊をテーマとし、葛飾北斎や村上隆の作品を展示した「Japan Supernatural」(2019年)、1990年代以降の日本の現代美術を紹介した「Time, light, Japan」(2016年)、インド国立博物館と共同で企画した「The Story of Rama: Indian Miniatures from the National Museum, New Delhi」(2015年)がある。また、草間彌生や李明維などのアーティストとの作品制作にも携わり、アジア美術の収集・研究・展示に深くかかわってきた。

撮影:Anna Kučera
メンター
会田 大也
山口情報芸術センター[YCAM] アーティスティック・ディレクター1976年東京都生まれ。東京造形大学、情報科学芸術大学院大学[IAMAS]修了。2003年より山口情報芸術センター[YCAM]にて教育プログラムの開発・運営を行い、2019年より学芸普及課長。国際巡回メディアアート展「MEDIA/ART KITCHEN」キュレーター(2013年)、東京大学大学院ソーシャルICTグローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム(GCL)特任助教(2014〜19年)、あいちトリエンナーレ2019および国際芸術祭「あいち2022」キュレーター(ラーニング)。
これまでミュージアム・エデュケーターとして、ミュージアムにおけるリテラシー教育や美術教育、地域プロジェクト、企業における人材開発等の分野で、ワークショップやファシリテーションの手法を用いて「学校の外の教育」を実践してきた。YCAMにおける一連のオリジナルメディアワークショップにてキッズデザイン大賞や、担当した企画展示「コロガル公園シリーズ」で文化庁メディア芸術祭、グッドデザイン賞などを受賞。

保坂 健二朗
滋賀県立美術館 ディレクター1976年茨城県生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程(美学美術史学専攻)修了。2000〜20年まで東京国立近代美術館(MOMAT)学芸員を経て、2021年より現職。
MOMATで企画した主な展覧会は「建築はどこにあるの? 7つのインスタレーション」(2010年)、「フランシス・ベーコン展」(2013年)、「声ノマ 全⾝詩⼈、吉増剛造展」(2016年)、「⽇本の家 1945年以降の建築とくらし」(2017年)。近年企画した展覧会には「人間の才能、生み出すことと生きること」(滋賀県立美術館、2022年)、「AWT FOCUS:平衡世界 日本のアート、戦後から現代まで」(大倉集古館、2023年)などがある。また、モスクワ市近代美術館、ハウス・コンストルクティヴ美術館(スイス・チューリッヒ)、MAXXI国立21世紀美術館(イタリア・ローマ)など、海外の展覧会の企画にも携わってきた。公益財団法人大林財団「都市のヴィジョン」推薦選考委員、文化庁文化審議会文化経済部門アート振興ワーキンググループ専門委員なども務める。

撮影:木奥 惠三
片岡 真実
国立アートリサーチセンター センター長、森美術館 館長1965年愛知県生まれ。ニッセイ基礎研究所にて文化芸術関連の研究員、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーターを経て、2003年より森美術館勤務、2020年より同館館長、2023年に国立アートリサーチセンター長着任。
2007~09年はヘイワード・ギャラリー(イギリス・ロンドン)にて、インターナショナル・キュレーターを兼務。第9回光州ビエンナーレ共同芸術監督(2012年)、第21回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2018年)、国際芸術祭「あいち2022」芸術監督。CIMAM(国際美術館会議)では、2014~22年に理事(うち2020~22年は会長)を務める。2018~22年度は「文化庁アートプラットフォーム事業」のステアリングコミッティー「日本現代アート委員会」座長。その他、文化審議会文化政策部会臨時委員、日本ユネスコ国内委員会委員など委員・審査員等多数。

撮影:伊藤 彰紀
安田 篤生
高知県立美術館 館長1963年大阪府生まれ。大阪大学文学部(美術史学専攻)卒。1987年より滋賀県立近代美術館、大阪府文化課、原美術館の学芸員を歴任し、1993年にアジア・ソサエティ(アメリカ・ニューヨーク)・フェローとして同附属美術館短期客員を務める。その後、原美術館学芸統括・副館長、奈良県立美術館学芸課長・副館長を経て、2024年より現職。
写真を中心に現代美術家の個展を多数担当。原美術館在職中に海外との協働機会も多く、ロサンゼルス・カウンティ美術館、オスロ国立現代美術館、サイ・トゥオンブリー財団(アメリカ・ニューヨーク)、ドイツ銀行アートコレクション等の海外キュレーターと協働し、コ・キュレーターとして企画展を担当した。また、同館が2003年から2021年の閉館までパートナーシップを結んだメルセデス・ベンツ日本株式会社との協働により、日本とドイツの現代美術のアーティストを相互派遣する「メルセデス・ベンツ アート・スコープ」にて、アーティスト・イン・レジデンスの成果展などを行ってきた。
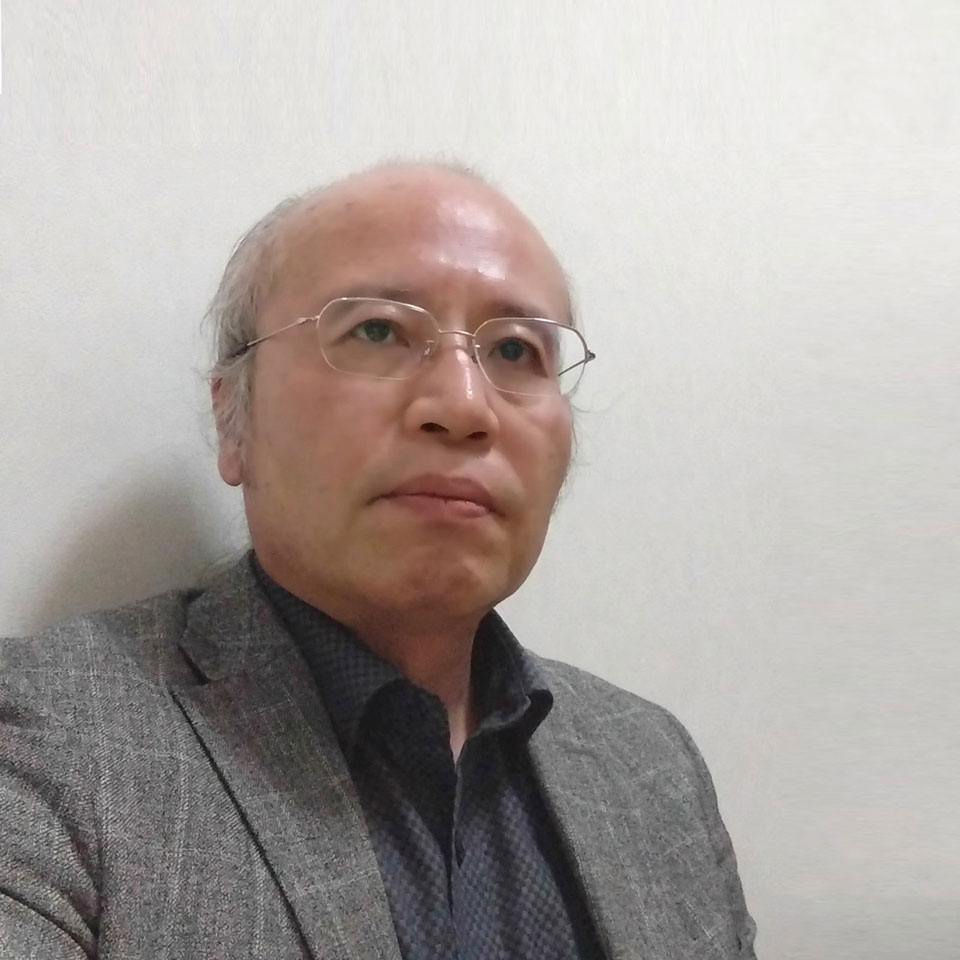
運営
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター(NCAR)
JUMPプログラム全体の企画統括と進行管理および情報発信を担っています。
国立アートリサーチセンター(NCAR)について
国立アートリサーチセンターは「アートをつなげる、深める、拡げる」をミッションに、情報収集と国内外への発信、コレクションの活用促進、人的ネットワークの構築、ラーニングの拡充、アーティストの支援など、日本の美術館活動全体の充実に寄与する活動に取り組んでいます。
https://ncar.artmuseums.go.jp









![山口情報芸術センター[YCAM]の写真](https://jump-ncar.artmuseums.go.jp/cms/wp-content/uploads/2025/07/ph_members_ycam-800x533.jpg)



